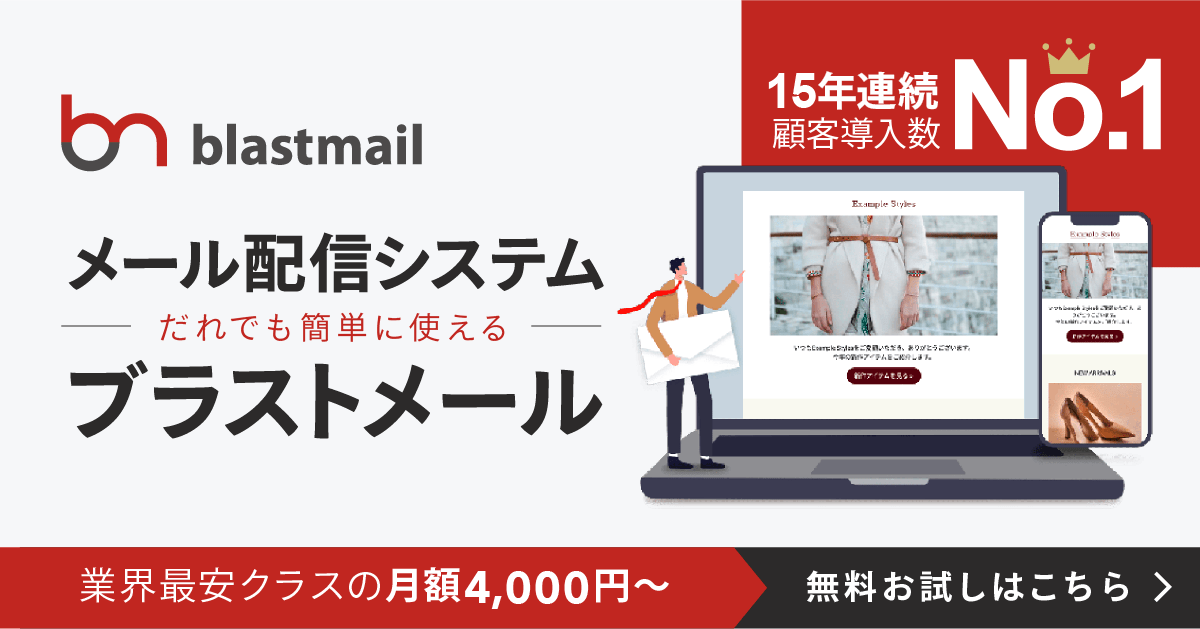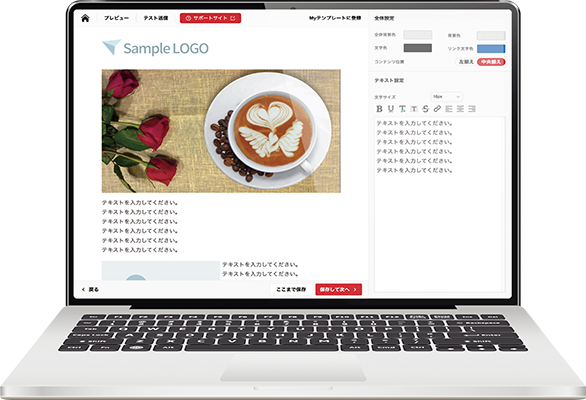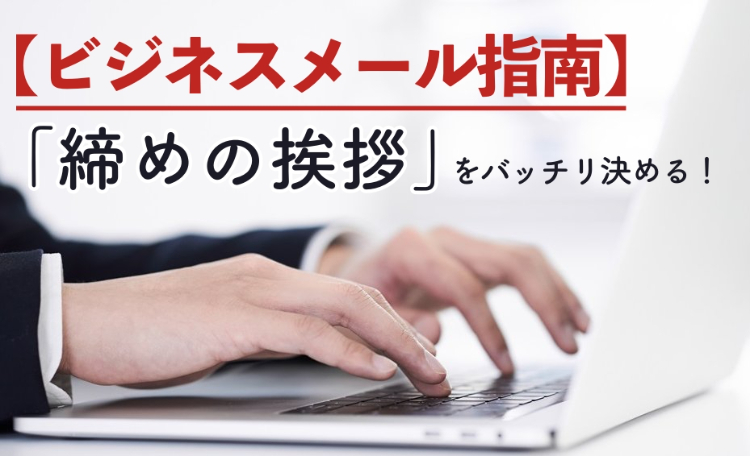
ビジネスメールでは本文の最後に「締めの挨拶」を添えることがマナーです。メールでは「拝啓」「敬具」などの挨拶言葉を省略します。メールではその代わりとして本文の前後に簡単な挨拶文を挟みます。ビジネスメールでは、用件だけでは素っ気なく、失礼な印象を相手に与えてしまいます。
また、メールの内容や相手に合わせた締めの言葉を使うことで、より親切な印象になり相手への配慮も伝わります。締めの言葉のバリエーションが少なくて困っているという方のために、シチュエーション別の例文も紹介しているのでぜひ参考にしてみてください。
ビジネスメールの上手な締め方
「メールの最後が上手く締まらない」「堅苦しい挨拶を考えるのが苦手」という方がいるかもしれませんが、以下で紹介するポイントと締めの挨拶の例文を覚えれば、その悩みは解消されます。ぜひ覚えてメールの締めの挨拶で悩む時間を減らしましょう。
相手に合わせた適切な挨拶を使う
締めの挨拶は、取引先、上司、同僚、部下など送る相手に合わせて使い分けましょう。
良く使われる「よろしくお願いします」といった挨拶も、部下や同僚であれば問題ありませんが、取引先や上司に送る場合には「ご検討お願いいたします」や「どうぞよろしくお願い致します」のように丁寧な言葉使いを意識しましょう。
また、冒頭の挨拶とのバランスも大切です。
冒頭の挨拶はとても丁寧なのに、締めの挨拶は軽薄、またその逆というのはメール全体の印象がおかしくなります。相手に、正しい文章が作れない人という印象を持たれかねないので、冒頭と締めの言葉使いのバランスにも注意しましょう。
クッション言葉を使う
文章の印象を柔らかく、温かみのあるものにするテクニックとして、「クッション言葉」がよく使われます。クッション言葉とは、相手への気配りや配慮を感じさせる言い回しのことです。以下はNG例です。
- 「〇日までに返信よろしくお願い致します。」
そのまま伝えると、やや事務的な印象を与えてしまうことがあります。そこでクッション言葉を添えて、以下のようにすると良いでしょう。
- 「ご多忙のことと存じますが、〇日までにご返信いただけますと幸いです。」
一言添えるだけでも、ぐっと丁寧で柔らかい印象になります。
メールは顔が見えないやりとりだからこそ、言葉の選び方ひとつで相手に与える印象が大きく変わります。クッション言葉を覚えておくと、お願いメールや催促メールなど、少し言いにくい内容を伝えるときにも役立ちます。
「取り急ぎ」の使い方
「取り急ぎ」とは「ひとまず急いで用件を伝えたい」という際に「取り急ぎご報告させていただきます」という形で使われます。ビジネスメールの締めでも良く使われている表現ですが「とりあえず急いで書いた」という意味合いも持つため、相手によっては悪い印象で受けとられる可能性があります。
マナー違反かどうかは微妙なところですが、目上の方に送る場合には「まずはご報告させていただきます」や「一旦、ご報告させていただきます」という言い換え表現の方が良いでしょう。また「取り急ぎ」という言葉を使った際には、改めて連絡を入れること、詳しくは電話で説明する旨を添えておくと相手も安心です。
季節感を反映させる
相手との関係性によっては、季節を考慮した時候の挨拶を締めの言葉として添えても良いでしょう。
例文は後ほど紹介しますが、年末であれば「今年もお世話になりました」、夏であれば「暑い日が続きますが体調にお気をつけください」など、季節感を考慮した締めの挨拶ができれば、より印象高いメールを作成できるでしょう。
ビジネスメールで使える締めの例文
それでは、ビジネスメールで使える締めの例文を紹介していきます。それぞれ、シチュエーション別にまとめているので、メールの内容に合わせて締めの言葉を選ぶようにしてください。
汎用性の高い締めの言葉
まずは、ビジネスメールにおいて頻繁に使われている締めの言葉を紹介します。
- よろしくお願いします
- よろしくお願い申し上げます
- どうぞよろしくお願い致します
- 引き続きよろしくお願い致します
- 何卒よろしくお願い致します
- 引き続きよろしくご協力を賜りたくお願いいたします。
- 今後ともご指導を賜りますようお願い申し上げます
- 今後も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます
これらの挨拶は汎用性が高く、様々なシーンで使えます。下の方の例文にいくにつれてよりフォーマルな表現になっています。
「ご厚誼(ごこうぎ)」とは「親しくお付き合いしてもらうこと」という意味です。あまり聞き慣れない言葉ですが、大切な取引先やお客様にメールを送る際には堅い表現も意識的に使いましょう。
お願い・依頼をする際の締めの言葉
お願いや、依頼メールの締めで使える例文の紹介です。上司や関係性の薄い取引先、業務状況によっては、お願いや依頼をしづらいという場面もあるでしょう。
そういった場合には、締めの挨拶をより丁寧に記すことで謙虚な印象のメールになります。
- ご検討のほどどうぞよろしくお願いいたします。
- ご多忙の折、お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします
- ぜひご出席くださいますよう、よろしくお願い申し上げます
- 誠に勝手なお願いではございますが、よろしくお願い申し上げます
- ご査収のほど、よろしくお願い申し上げます
- お力添えくださいますよう、よろしくお願いいたします
- ご一考いただけますと幸いです
- 早急に善処していただきますようお願い申し上げます
先ほど紹介した「クッション言葉」を使用し、なるべく柔らかい言葉使いになるよう意識しましょう。
お願い・依頼メールの上手な書き方については上記の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
感謝の気持ちを伝える際の締めの言葉
お礼メールの締めの挨拶の例文です。
本文だけでなく、締めの挨拶も気を使い、より相手に感謝の気持ちを伝えれるようにしましょう。
- この度は心より感謝申し上げます
- 重ねてお礼申し上げます
- 厚く御礼申し上げます
- ご厚情を賜り、誠にありがとうございます
- この度の件につきましては、謹んでお礼申し上げます
お礼メールを書くコツはこちらの記事でも詳しく解説しています。
関連記事:「お礼メール」で相手に感謝を伝えるには?お礼メールを書くコツ & コピペで使える例文をご紹介!
お詫び・謝罪の際の締めの言葉
謝罪メールの締めの例文です。
トラブルが起こった際の事後処理で、企業の印象は大きく変わります。事態を大きくさせないよう、より慎重な言葉使いを意識しましょう。
- 多大なご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございませんでした
- ご迷惑をおかけしましたことを深く反省しております
- 幾重にもお詫び申し上げます
- この度の件につきまして、謹んでお詫び申し上げます
- この度は何とぞご容赦くださいますよう、お願い申し上げます
- ご理解の上、ご容赦くださいますよう平にお願い申し上げます
ミスが起こった際には、まずは現場に出向くか電話にて直接謝罪するのがマナーです。ミスが起こってからの対応スピードはその後のお互いの信頼関係に大きく影響します。謝罪メールはすぐに電話対応や現場に出向けないといった場合に使われます。
また、直接謝罪できた場合にも、改めてメールにて謝罪文を送ることもマナーの一つです。
関連記事:【ビジネス向け】誠意が伝わる謝罪文を書くためのポイントと例文
こちらの記事では、謝罪メールを作成する際のポイントや、謝罪の際に良く使われるフレーズ、シチュエーション別の例文を詳しく解説しているので参考にしてみてください。
時候の挨拶を使用した締めの言葉
先ほども少し説明しましたが、季節の挨拶も締めの言葉として取り入れらます。
日本には「暑中見舞い」や「寒中見舞い」など、季節ごとにお世話になっている人に挨拶状を送る文化があります。わざわざ、はがきで送るまでいかなくとも、メールでそうした気遣いがあるだけで、相手からの印象も良くなるはずです。
- 梅の便りが聞かれる昨今、皆様のご健勝を心よりお祈りいたします
- 暦の上に春は立ちながら、厳寒の折でございます。何卒ご自愛されます様お願い申し上げます
- 今しばらく鬱陶しい毎日でございますが、何卒お体大切にお過ごしください
- 厳しい暑さが続いておりますので、お体ご自愛下さい
- 紅葉の美しい時期になりましたが、体調を崩されませんようお気をつけください
- 寒暖差の激しい時期になりますが、皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます
- どうぞおすこやかに新年を迎えることができますよう、お祈り申し上げます
- 余寒厳しき折、どうぞお身体を大切になさってください
各季節、月ごとの挨拶の例文は以下でまとめています。「今の時期はどのような挨拶をすれば良いんだろう」と迷った際には参考にしてみてください。
関連記事:【季節の挨拶】 冬の時期に使える挨拶メールのご紹介
コロナを気遣う締めの挨拶
新型コロナウイルスによる影響はまだまだ続いています。
ビジネスメールの締めでも企業間でお互いを気遣う挨拶ができると良いでしょう。
- 先の見通しがつき辛い日が続きますが、寒さ厳しい歳末の時節柄、何卒ご自愛のほどお願い申し上げます。
- このような状況ではありますが、皆様には健やかにお過ごしになれますようお祈り致します。
- 感染の不安があると存じますが、くれぐれもご自愛ください。
コロナ禍の挨拶文の書き方はこちらの記事にて詳しく解説しています。
コロナ禍のあいさつ文はこう書く! 相手を気遣う挨拶メールの例文をご紹介
相手への配慮を示す「返信不要」の締め方
ビジネスメールにおいて相手に返信の手間を取らせないよう配慮することも、円滑なコミュニケーションにおける重要なマナーの一つです。情報共有や確認のみが目的の場合、あえて「返信不要」と書き添えることで相手のタスクを減らし、時間を有効に使ってもらうことにつながります。
ただし、伝え方によっては冷たい印象や指示のような響きを与えかねません。状況や相手との関係性に応じて適切な表現を選ぶことが大切です。
明確に「返信不要」と伝える際の例文
主に社内連絡や情報共有が目的で、相手の確認作業(「承知しました」など)を明確に不要としたい場合に用います。相手のタスクを確実に減らしたいという意図が伝わります。どのような状況で使うかによって、以下のように使い分けると良いでしょう。
- 単なる情報共有の場合 「なお、本メールは情報共有のみとなりますので、ご返信には及びません。」
- 資料などを確認してほしいが返信は不要な場合 「添付の資料をご確認ください。特に問題ないようでしたら、ご返信は不要です。」
- メールの末尾で簡潔に伝えたい場合 「以上、よろしくお願いいたします。(ご返信は不要です)」
相手の負担を減らす「確認のみ」のニュアンス
「返信不要」と明記するほどではないものの、相手に「返信しなければ」というプレッシャーを与えたくない場合に有効な表現です。直接的ではないため、やや柔らかい印象を与えます。例えば、資料を送付した際や、簡単な進捗報告のメールなどで使われます。これらの表現でメールが終わっていれば、受け手は「確認さえすれば返信は必須ではない」と解釈するのが一般的です。
- 取り急ぎ、ご報告まで。
- お目通しいただけますと幸いです。
- (資料送付の際など)ご査収のほど、よろしくお願いいたします。
目上の人にも失礼のない「返信不要」の伝え方
目上の方や取引先に対して「返信不要です」と伝えると、命令形のように受け取られたり突き放したような印象を与えたりするリスクがあります。相手への敬意を示しつつ返信の手間をかけさせたくないという配慮を伝えるためには、より丁寧なクッション言葉を使う必要があります。
- ご多忙のことと存じますので、ご返信はお気遣いなさいませんようお願い申し上げます。
- ご確認いただければと存じます。なお、ご返信はいただかなくても問題ございません。
- 皆様へのお知らせとなりますため、本メールへのご返信はご無用です。
一斉配信でも締めの言葉は必要
1対1のメールだけではなく、一斉配信を行う際にも締めの言葉は必要です。
基本的には先述した通りの使用方法ですが、一斉配信を行う際はBcc配信ではなく、ツールを導入するのがおすすめです。
下記の記事ではおすすめのメール配信システムをまとめているので、参考にしてみてください。
関連記事:メール配信システム比較20選!機能・料金を徹底比較
まとめ
以上、ビジネスメールの締めを書く際のポイントや、実際に使える例文を紹介してきました。締めの言葉はメール全体の印象を左右しかねない重要なポイントです。
締めの言葉は、はじめはどのような文言を使えば良いのか悩むかと思いますが、ある程度形式が決まっており「常套句」のようなものが存在します。いつも決まった締めの挨拶ではなく、今回紹介した例文を参考に、メールの内容や送る相手に合わせて締めの言葉を選んでいくようにしましょう。