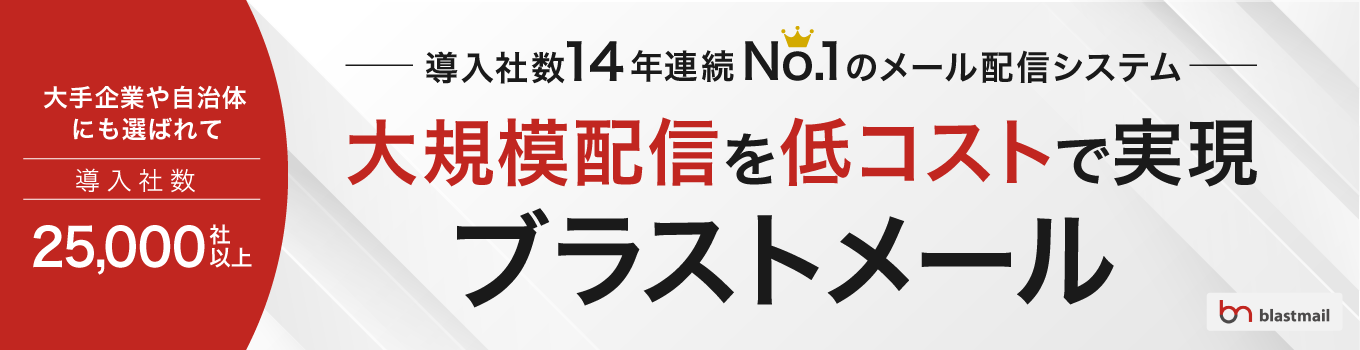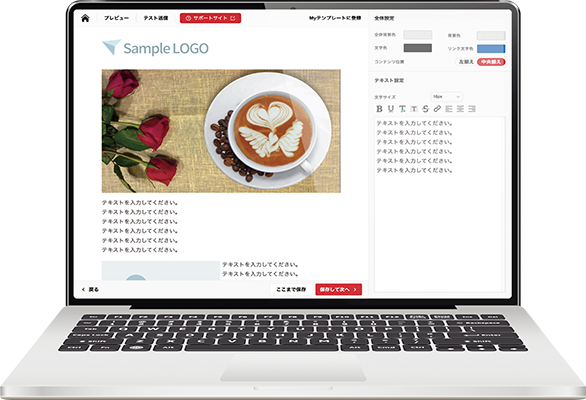2024年に実施されたGmailのガイドライン変更により、多くの企業がメール配信環境の見直しを迫られました。そしてそれに続く形でMicrosoft(Outlook)もまた、迷惑メール対策の強化に向けた新たな一歩を踏み出しています。
「最近、Outlook宛てのメールが届きにくくなった気がする」 「2025年5月から始まる規制強化について、具体的に何をすればいいかわからない」もしあなたがこのような不安をお持ちなら、この記事を参考にすると良いでしょう。
MicrosoftはOutlookやHotmail宛に1日5,000通以上のメールを送信する送信者に対し、新たな認証要件を適用することを発表しました。この対応を怠ると大切なメールが「迷惑メール」として処理されたり、最悪の場合はブロックされたりするリスクがあります。
本記事では非技術者の方でも理解できるよう、Outlookの新しい送信者ガイドラインの重要ポイントと、確実にメールを届けるために今すぐ始めるべき「3つの認証対策」についてわかりやすく解説します。自社の利用しているメール配信システムがきちんと基準を満たしているか確認し、リスクに備えられるようにしましょう。
※掲載原文はマイクロソフトの公式サイトの発表をご確認下さい。
この記事の要約
- 対象者は1日5000通以上の配信を行うドメイン
- SPF/DKIM/DMARCの設定が必須になる
- 迷惑メール報告基準を0.3%以下に保つ必要がある
- 有効なFromアドレスを利用する必要がある
- その他にも推奨要件多数
- 上記に対応できていないとOutlookあてには届かない可能性がある
目次
Outlookの送信者ガイドラインの変更でそもそも何が変わるのか?
Microsoft(Outlook.com/Hotmail)は、迷惑メール(スパム)の増加やなりすましメール(フィッシングなど)の脅威に対応するため、「大量にメールを送る送信者」に対して、新たな認証ルールや運用ルールの順守を義務化します。
要件を満たしていないメールはどうなる?
上記認証要件を満たしていないメールについては、2025年5月5日以降、まずOutlook.com受信側で迷惑メールフォルダ(Junk)に振り分けられる措置が開始されます。
これは送信者に設定不備を是正する機会を与えるための段階的措置であり、問題が解消されない場合、将来的にはそうしたメールを受信拒否(ブロック)する方針であることも明言されています。
したがって、大量送信を行う送信者は遅くとも施行開始の2025年5月までにSPF/DKIM/DMARCの実装と設定確認を済ませておく必要があります。
対象企業
Microsoftが今回のポリシーで対象としている「大量送信者(bulk sender)」は、Outlook.com/Hotmail/Live宛てに5,000通/日以上のメールを送信するドメインを指します。
この条件に該当する送信者(ドメイン)は、2025年5月5日以降、自ドメインにSPF・DKIM・DMARCレコードを正しく設定していない場合メールが受信者の迷惑メールフォルダ行きとなるなどの影響を受けます。
逆に言えば、1日あたり数千通程度を大きく下回るような小規模送信者は本ポリシーの直接的な強制対象ではありません。
しかしMicrosoftは、5,000通未満の送信者であってもこれらの認証技術を導入することが望ましいベストプラクティスであると述べています。送信ドメインの信頼性確保やブランド保護、メール到達率向上のため、DMARCを含む認証対策はすべての送信者にとって有益であり、規模に関わらず取り組むことが推奨されています。
参考記事:techcommunity.microsoft.com
※GmailやYahoo宛にもメールを送っている場合、同様のルールが既に適用中です(Googleは2024年2月から義務化済)
必須となる3つの認証(SPF・DKIM・DMARC)
Gmailのガイドラインでは状況によって一部の認証のみで通過できるケースもありましたが今回のMicrosoftの新要件ではより厳格な対応が求められます。基本的にはSPFとDKIMおよびDMARCの3つすべてを導入する必要があります。
特にDMARCの設定はなりすましメール対策として必須項目となっておりポリシー設定を含めた適切な運用が欠かせません。送信ドメインの正当性を証明するためこれら3つの認証技術をセットで実装しセキュリティレベルを最大化しておきましょう。これらの詳細は次のパートで解説します。
今回新たにOutlookが求める要件:送信ドメイン認証
今回の信用件で最も重要で対応が必要な案件は「送信ドメイン認証」です。
大規模送信者は自ドメインでSPF・DKIM・DMARCを正しく実装し、それぞれの認証チェックを合格 (Pass) させる必要があります。
SPF(Sender Policy Framework)
送信ドメインのDNSにそのドメインから送信を許可されたIPアドレスやホスト名を正確に列挙し、メール送信時のSPFチェックを合格させることが求められます。
受信側では送信元IPがドメインのSPFレコード内に含まれているか検証されます。
SPFについての詳しい内容は以下の記事に記載されています。
DKIM(DomainKeys Identified Mail)
ドメインの秘密鍵でメール(ヘッダ等)に電子署名を付与し、受信側で公開鍵による署名検証が合格となるよう設定することが求められます。
これによりメールの完全性と送信元ドメインの真正性が保証されます。
DKIMについての詳しい解説は以下の記事に記載されています。
DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance)
ドメインにDMARCレコードを公開し、最低でもポリシーp=none(モニタリング用途のポリシー)を指定することが求められます。
加えて、送信元のFromドメインがSPFまたはDKIMで認証されたドメインと整合(アライメント)していなければなりません。
可能であればSPF・DKIMの両方がFromドメインと一致することが望ましいです。
DMARCについての詳しい解説は以下の記事を参照してください。
その他のOutlookが推奨する要件
今回の送信者向けの要件は「送信ドメイン認証」についてですが、過去に定められたものや推奨されている要件は他にもあります。
マーケティングや配信の実務にかかわるのものあるので、この機会に確認しておきしょう。
有効な送信元アドレスの使用
メールのFromアドレスおよびReply-Toアドレスには、有効で実際に受信可能なアドレスを使用しましょう。
送信ドメインと無関係なアドレスや返信不能なアドレスを使うことは避け、ユーザから返信があれば適切に受け取れるようにします。
例えば「no-reply@…」のようなアドレスを用いる場合でも、そのメールボックスを監視し返信に対応できる体制を整えることが望ましいです。
配信停止(unsubscribe)オプションの明示
特にマーケティングやニュースレター等の一斉送信メールには、受信者が簡単に配信停止を行える明確なリンク(「ここをクリックで配信停止」等)をメール本文中に設置してください。
リンクはメールの目立つ箇所に配置し、クリックするだけで確実に配信停止が処理されるようにします。
また可能であれば、メールヘッダにList-Unsubscribeヘッダを追加し、ワンクリック配信停止(RFC8058準拠)に対応することも推奨されます。
これによりOutlook.com以外のメールクライアントやサービス(例: Gmailの「このメールを登録解除」ボタン)からの自動解除にも対応できます。
メールリストの衛生管理
配信リストを定期的にクリーンアップし、存在しないアドレスや長期間届いていないアドレス、反応のないアドレスはリストから削除しましょう。
送信のたびに発生するバウンス(送達不能メール)を監視し、エラーコードが「恒久的失敗(5xx系)」を示すアドレスには繰り返し送らないようにする必要があります。
適切なバウンス処理とリスト管理により、無駄な送信を減らすとともに、スパム苦情やアウトルック側からの評価低下を防ぐことができます。
透明なメール送信方法
メールの件名・本文・ヘッダにおいて誤解を招く表現や利用者を欺くような情報を含めないようにしましょう。
また受信者がそのメールを受け取ることに同意している(オプトイン済みである)ことを必ず前提としてください。
これらの透明性ある運用を守ることで、結果的にユーザーからの信頼度が増し苦情も減少します。
Microsoftも「受信者の同意を得た上で送信する」「ヘッダを偽装しない」等の健全なメール送信プラクティスの遵守を強く推奨しています。
一般的にメール配信において推奨される要件
今回のMicrosoftからの発表に記載はありませんが、その他GmailやYahoo!メールに対して一斉送信を行際に必要な要件についても確認しておきましょう。
TLS暗号化
2025年5月からの新要件においてTLSでの送信が必須とされる旨の記載はありません。
ただし、TLS暗号化は現在のメール送信における標準的なセキュリティ対策であり、Google Gmailなど他の主要プロバイダでは「メールは必ずTLS経由で送信する」ことが事実上の必須条件となっています。
そのため、Outlook.com向けのメール送信においてもTLS対応のメールサーバーを使用し通信を暗号化することが強く推奨されます(新要件に直接含まれていなくとも、TLS非対応の送信はセキュリティ上リスクとなり得ます)。
迷惑メール報告率を0.3%未満を維持する
Outlookユーザーが受信したメールを「迷惑メールとして報告」した割合が0.3%を超えると、ブロックや受信拒否の対象になる可能性があります。
配信リストに古いアドレスや低エンゲージメントのユーザーが多く含まれていたり、内容や件名が不適切な場合は、報告率が跳ね上がるリスクがあるため注意しましょう。
迷惑メール率を下げるために行えることは以下のとおりです。
- 配信対象を常に更新してリストを健全な状態に保つ
- 過度な広告や古代表現を避け、件名や内容で誤解を与えない
- ワンクリックで解除できるリンクを設置しておく
- 配信頻度やタイミングを最適化する
送る相手と内容をきちんと見極めユーザーにストレスを与えない配信設計を行うことで、単に迷惑メール判定やブロック回避のみならず、マーケティングの効果を最大限に発揮することにもつながります。日ごろから誠実な配信を心がけましょう。
要件一覧表
今回の要件をまとめた表を作成したので、対応できているか確認しましょう。
| チェック項目 | 確認・対応内容 | 担当 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SPF設定済みか? | ITチームまたはシステム会社に「SPF設定済みか確認してください」と依頼 | 技術担当 | DNS設定で送信元IPを定義 |
| DKIM署名されているか? | メール送信時にDKIM署名されているか確認 | メール配信ベンダー | 多くの配信システムではON/OFF設定あり |
| DMARCポリシー(p=none以上)設定済みか? | DMARCレコードがあるか確認 | IT or ベンダー | 最低限p=none(モニタリング用)を設定 |
| FromドメインがSPFまたはDKIMと一致しているか? | 送信元表示名(@example.com)が認証ドメインと同じか | マーケ担当&技術 | メールヘッダで整合性確認できる |
| 配信停止リンク(unsubscribe)があるか? | HTMLメール本文に「配信停止」リンクがあるか | マーケ担当 | クリック1回で停止できるのが理想 |
| 差出人アドレスは返信可能か? | no-replyでなく「support@~」など応答できるアドレスを使用 | マーケ/CS | 問い合わせ対応を考慮した設計を |
| バウンス・未達アドレスは除外しているか? | 届かないアドレスには繰り返し送らない | CRM/配信ツール設定 | 配信停止リスト管理が重要 |
| 苦情率(迷惑メール報告)が高くないか? | Outlook側のSNDSツールなどで確認可能 | 技術 or ベンダー | 0.3%未満を目指す |
Outlookでの到達率を可視化する「SNDS」の活用
GmailにおけるPostmaster ToolsのようにMicrosoftにも送信メールの評価を確認できる専用ツールが存在します。Outlook宛てのメールが正しく届いているか不安な場合はSNDSという無料サービスを活用して現状を把握しましょう。ブラックリスト登録のリスクを早期に検知するためにもSNDSの導入は非常に有効です。
SNDS (Smart Network Data Services) とは?
SNDSはMicrosoftが提供する送信元IPアドレスの評価ツールです。自社のIPアドレスから送信されたメールがOutlook側でどのように判定されているかをデータとして確認できます。具体的には送信通数や迷惑メール判定率およびスパムトラップへのヒット状況などが可視化されます。
このデータを見ることで「なぜ届かないのか」の原因を特定しやすくなり具体的な改善策を立てることが可能です。登録は無料ですので大量配信を行う送信者は必ず設定しておきましょう。
SNDS公式ページ:https://sendersupport.olc.protection.outlook.com/snds/index
JMRP (Junk Mail Reporting Program) への登録
SNDSと合わせて活用したいのがJMRPというプログラムです。これはOutlookユーザーが受信トレイで「迷惑メール」ボタンを押した際にその情報を送信元へフィードバックしてくれる仕組みです。
送信者はどのメールが迷惑判定されたかを把握できるため配信リストから該当アドレスを除外するなどの対応が迅速に行えます。ユーザーからの否定的な反応を放置するとドメイン評価が下がり続けるためJMRPからの通知を受け取れる体制を整えることが重要です。
JMRPへの参加・設定はこちら(SNDS内):https://sendersupport.olc.protection.outlook.com/snds/JMRP.aspx
一斉配信にはメール配信システムを使おう
大規模なメール送信を行う際は「メール配信システム」の利用をおすすめします。ここでは、メール配信システムのメリットについて説明します。
宛先リストの管理が容易
メール配信システムにはセグメント配信機能がついていることが多く、送信先を容易に調整できます。Gmailなどのメーラーでも可能ではありますが、誤送信等のリスクがあるので、あまりおすすめのやり方ではありません。
大量のメールを一度に効率的に送信できる
メール配信システムは多くの場合、大量送信に適したサーバーを使用しているので、一度に大量のメールを送ることができます。また、有料サービスの場合、送信通数やアドレス数に応じて料金が設定されているので、自分に合ったシステムを導入すれば、低価格で大量のメール配信が可能です。
特にブラストメールは、アドレス数に応じた料金プランなので、配信数の少ないメルマガ初心者にもお得に使えるサービスです。
HTMLメールを知識なしで作成できるエディタがある
メール配信をマーケティング目的で行う場合、HTMLメールの利用は必須です。
メール配信システムにはHTMLメールを知識なしで直感的に操作できる「エディタ」やあらかじめ構成が組まれている「テンプレート」といった機能が備わっています。
エディタの使いやすさはシステムによってさまざまなので、必ず無料トライアルなどで操作感を試してから選びましょう。
スパムフィルタ対策が充実している
メール配信システムにはドメイン認証などセキュリティに特化した機能が備わっています。また、信頼度の高いIPアドレスを保有していることも多く、通常のメーラーで配信を行うよりも到達率が高くなります。
セキュリティ上のリスクを抑えられる
誤送信やCC/BCC間違いといった人的エラーから生じる情報漏洩といったリスクも最小限に抑えられます。
配信の分析ができる
メール配信システムは多くの場合、到達率や開封率、クリック率といった指標の分析が可能です。
特にメルマガを送りたい場合、施策の効果測定は必須です。通常のメーラーを使った一斉送信ではどれだけ届いたか、何人が開封したか、といったデータが全く取れません。
メルマガを送りたい人にはメール配信システムの利用を強くお勧めします。
参考記事:メール配信システムおすすめ比較20選!専門家が図解とランキング形式で解説
大手メーラーの送信者ガイドラインに準拠している
有料のメール配信システムは、Outlookの新ガイドラインはもちろん、すでに施行されているYahoo!やGoogleのガイドラインにも原則準拠したつくりになっています。
DKIMの設定サポートなどを受けられるシステムもあるので、社内にエンジニアがいない場合はメール配信システムの導入をお勧めします。
メール配信システムの選び方
メール配信システムには多様なサービスがあるので、自分に合ったサービスを選ぶことが大切です。
ここでは、メール配信システムを選ぶ時のポイントについて解説します。
配信規模と料金プラン
メール配信システムは、配信規模によって最適な料金プランが異なります。少量のメールであれば無料プランでも十分ですが、配信リストが増えたり、頻繁にメールを送信する場合は有料プランをお勧めします。
配信先の安全性と到達率
到達率も非常に重要です。SPF(Sender Policy Framework)やDKIM(DomainKeys Identified Mail)といった、メールの正当性を保証するための認証プロトコルに対応していないと、メールがスパム扱いされる可能性が高くなります。
特にGmailは送信者ガイドラインもアップデートされているので、これらの対策がなされているシステムを選ぶのは必須といえるでしょう。
関連記事:【解決策】2024年2月よりGmailガイドラインが変更!1日5000件以上の配信は対応必須!
サポート体制
メールの一斉送信は個人情報を扱う非常にデリケートな領域なので、万が一の際のサポート体制は非常に重要です。特にチャットサポートや電話サポートといった、リアルタイムのサポートが提供されているか、日本語でのサポートがあるかは重要なチェックポイントになりえるでしょう。
機能の充実度
メール配信システムには、セグメント機能や効果測定など、様々な付加機能が用意されています。必要な機能が揃っているか確認しましょう。
また、不必要な機能がついていることで、金額が高くなっているケースもあります。本当に自社で必要な機能は何かを考えたうえで、必要最低限のプランを選ぶことをおすすめします。
使いやすさ
メルマガ初心者の場合、いきなり高度なデザインの入ったメールを0から作成するのは非常に難易度が高いです。また、管理画面の見やすさも、メルマガの運用をしていく上では非常に大切です。
無料トライアルやFreeプランを提供しているサービスは、実際に使ってみることができるので、自分に合ったサービスを探すのに役立つでしょう。
大規模メール配信を行うならブラストメール(blastmail)
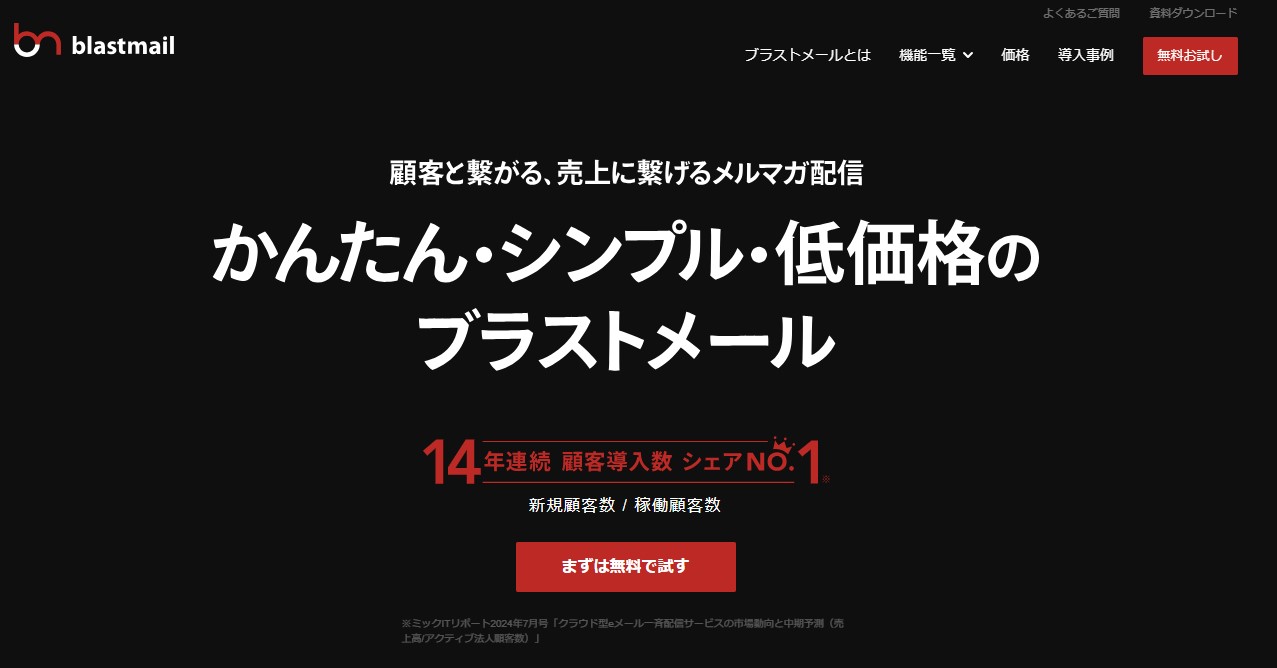
ブラストメールは、15年連続で顧客導入シェア1位を獲得している信頼性の高いメール配信システムです。さまざまな業種や官公庁でも利用されており、定番のメール配信システムとして広く知られています。
HTMLメールエディタはもちろん、セグメント配信や豊富なテンプレート、迷惑メール判定対策機能など、メールマーケティングに必要な基本的な機能はすべて揃っています。最も安いプランなら、月額4,000円で導入することができます。
また、配信速度が高く、到達率が非常に高い点も魅力です。
「安心してメール配信を行いたい」「たくさん機能があっても使いこなせない」「大切な情報を確実に届けたい」といった方にはブラストメールがおすすめです。
無料トライアルも用意されているので、まずは試してみることをお勧めします。
FAQ
- Q:Outlookの新ガイドラインで特に重要な要件は何ですか?
- A:1日5,000通以上の送信者に対し、SPF・DKIM・DMARCの送信ドメイン認証設定が必須化されました。特にDMARCの実装に加え、迷惑メール報告率を0.3%以下に抑える運用管理が重要な要件となります。
- Q:どのような送信者が今回の規制の対象になりますか?
- A:主にOutlookドメイン宛てに1日5,000通以上のメールを送信する一斉配信者が対象です。ただし、メールの到達率を維持するためには配信規模に関わらず、すべての送信者が本ガイドラインに準拠することが推奨されます。
- Q:対応しなかった場合、メール配信にどのような影響がありますか?
- A:要件を満たしていない場合、メールがブロックされたり、迷惑メールフォルダに振り分けられたりするリスクが高まります。Outlook宛てのメールが正しく届かなくなる可能性があるため、SPF・DKIM・DMARCの設定状況を早急に確認する必要があります。
- Q:迷惑メール率やリスト管理についてはどうすればよいですか?
- A:迷惑メール率を低く保つことに加え、無効なアドレスへの送信を防ぐ「リストの衛生管理」が求められます。送信エラー(バウンス)を監視し、恒久的なエラーとなったアドレスには再送しないようリストから除外する運用を徹底してください。